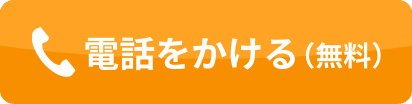ナーチャリングとは?事前の注意点やプロセスの詳細を解説
更新日:2023.09.29
「ナーチャリング」は、2023年現在インターネットマーケティングに欠かせない手法となっています。
しかし、ナーチャリングの必要性やメリットが分からない状態では、コンテンツの制作で役立てられません。
今回は、ナーチャリングのメリットや手法が分かるように解説しただけではなく、事前の注意点も紹介しています。
この記事を読むことで、ナーチャリングへの取り組み方が分かるでしょう。
「ナーチャリングとは」を簡単に解説
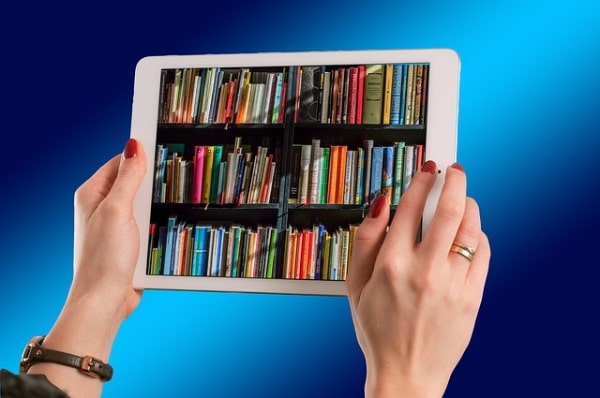
ナーチャリングとは、自社の商品やサービスに興味を持ってくれている「見込み客」を、顧客またはリピーターに育成していくことを表しています。
効率的な売り上げのアップが見込めるので、新規顧客へのアプローチだけではなく、既存顧客へのナーチャリングも欠かせません。
インターネットの発達によって、ユーザーと企業の接点が多様化しているので、集客するためには見込み客に選ばれる企業になる必要があります。
見込み客に選ばれる企業になるためにも、顧客への育成がポイントになります。
ナーチャリングはなぜ必要なのか

ナーチャリングの実施により、自社と見込み客との接点が増加します。見込み客との接点が増加したことで、自社は多くのメリットを得ることが可能です。
顧客の自然消滅を防ぐから
多くの場合、企業が抱えている案件はひとつだけではなく、複数の顧客を同時に対応しています。
複数の顧客を同時に対応している中で、見込み客の育成が長期化すると、追客を忘れてしまうといったミスが多発するでしょう。
追客を忘れてしまうと、長期間にわたって顧客になってくれる可能性があった見込み客が自然消滅してしまいます。
見込み客が自然消滅してしまうと自社の売り上げに繋がりませんが、ナーチャリングによって接点を持ち続けることが可能です。
競合他社との差別化ができるから
ユーザーの価値観が多様化している現在では、どんなにニッチだと思われるサービスでも、競合他社が存在します。
値段が高いサービスであればあるほど、売り上げに繋がるので、競争は激化します。
競合他社との競争が激化する中で自社のサービスを選んでもらうには、営業活動といった付加価値が欠かせません。
ナーチャリングは、営業活動の一環として、見込み客を育ててくれるのです。
営業活動の一環なので、企業全体のコミュニケーション能力が高まると、見込み客を育成する能力に繋がっていきます。
ナーチャリングを実施する2つのメリット

ナーチャリングのメリットを確認することで、必要性が理解できます。
営業の効率アップ
ナーチャリングは成約率を高めるので、営業の効率アップに繋がります。
自社がBtoBのビジネスに携わっている場合、サービスの認知から購買決定までに時間がかかることは知っているでしょう。
BtoBは個人で動く場合とは異なり、Webサイトを閲覧している人と、購買決定の権利を持っている人が異なるからです。
また、見込み客は、最終的に自社の売上に貢献することを念頭に置いてWebサイトを閲覧するので、購買の基準も厳しくなります。
見込み客の興味や関心が薄い状態で営業をしても、自社の売り上げや認知拡大に貢献しないサービスだと思われて購入してもらえません。
しかし、見込み客に対してサービスの機能や役立つ情報をしっかりと伝えるナーチャリングでは、興味や関心が高まった状態でアピールすることが可能です。
すでに興味や関心が高い見込み顧客に営業するので、ナーチャリングによって営業の効率アップに繋がっていきます。
顧客の単価アップ
ナーチャリングでは、見込み客にサービスの詳細をきちんと伝えるので、顧客の単価アップに繋がります。
例として、自社が値段の異なる複数のプランを用意していると考えてください。
複数のプランが存在する場合、見込み客は「違いがよくわからないからとりあえず一番安いプラン」を選択することが多いです。
しかし、ナーチャリングによって値段が高いプランの良さが分かっていると、「メリットが多いから値段が高いプランを使ってみよう」と考える見込み客もいます。
ナーチャリングを実施する前の注意点

ナーチャリングを実施する前には注意点があります。
計画に時間をかけすぎない
ナーチャリングを実施する際は、計画を立てることに時間をかけすぎないようにします。
計画は、性格がまじめなほど時間を立ててきちんと作りこみますが、ナーチャリングの目的を忘れてはいけません。
ナーチャリングは見込み客を育成することなので、運営にはある程度の時間がかかります。
インターネット社会は動きが速いので、時間をかけて計画を立てているうちに状況が変化してしまうこともあるでしょう。
ナーチャリングを成功させるには、目に留まった手法をはじめてから、PDCAサイクルを回していく考え方も必要です。
営業とマーケティングの連携が重要
ナーチャリングは、営業とマーケティングの連携から始めることで、滞りなく進めることができます。
見込み客の中でも、自社のサービスに対して強く関心を持っている層に対してアピールする必要があるからです。
自社のサービスに対して強く関心を持っている層を見つけるには、営業とマーケティングが協力することが欠かせません。
ナーチャリングを実施するために社内で調整をする場合でも、営業とマーケティングの連携を意識しておきましょう。
ナーチャリングの2つの手法を解説

注意点が理解できたら、いよいよナーチャリングの手法を見ていきます。
メルマガの配信で見込み客との接点を作る
メルマガは、見込み客と定期的に接点を作れる有力なツールです。
見込み客と接点を持ち続けていると、購買決定などの重要なシーンで思い出してもらえるようになります。
メルマガにおいても、インターネット上のコンテンツ制作と同様に、見込み客が求める情報を意識しながら配信していくことが重要です。配信側が伝えたいことを一方的に掲載するのではなく、「見込み客が知りたいことは何か」を常に意識することで成功に繋がります。
メールの機能を効果的に使う
メルマガには、ひとり一人の状態に合わせて配信できる「ステップメール」という機能があります。
個人に向けたメールなので、見込み客の状態と配信する内容を合わせられます。
また、メルマガでは「Aの情報に興味を持ってくれたユーザー」「Aの情報ではなくBの情報に興味を持ってくれたユーザー」のように、見込み客に適した情報発信が可能です。
メールの機能を効果的に活用すると、段階に合わせて見込み客を育成することができます。
オウンドメディアで情報発信をする
オウンドメディアとは自社が所有するブログのことを表していて、SNSや広告出稿などの組み合わせによって相乗効果が期待できます。
ユーザーがサービスを購入して自社の売り上げに繋げることがオウンドメディアの役割なので、見込み客に適したアプローチがポイントです。
オウンドメディアを制作するには、目的の設定やコンテンツの設計などが重要ですが、ここでは誤解しがちなSEOについて解説していきます。
SEOを理解すること
オウンドメディアを成功させるには、SEOを理解してユーザーの知識レベルに合わせた情報発信をすることです。
SEOは「検索エンジン最適化」のことで、Googleのシェアが最も多くなっています。
「検索エンジン最適化」といえば、Googleで上位表示させるための対策だと考えておくといいでしょう。
あらゆる知識レベルのユーザーが、検索エンジンを使ってさまざまなキーワードで検索します。サービスについての知識がほとんどないユーザーに対して難しいスペックを発信しても、見込み客の育成にはなりません。
そのため、オウンドメディアはキーワード選定と、ユーザーが求めている情報への理解が必要不可欠です。
オウンドメディアで記事を執筆する際は、個人ブログと同様に「このキーワードで検索するユーザーの知識レベルはどの程度なのか」ということをしっかりと考えてください。
SEOの基本はユーザーファースト
キーワード選定以外にも、スマートフォンでの表示を最適化したり、ページの構造を分かりやすくしたりと、オウンドメディアのSEOにはさまざまな方法があります。
難しく考えてしまいがちですが、オウンドメディアを閲覧するユーザーのことを考えることが、SEOの基本です。
ユーザーのことを考えてオウンドメディアを制作すれば、コンテンツに必要なテクニックなども後からついてくるでしょう。
ナーチャリングの鍵|オウンドメディアの作り方

ナーチャリングを始めると、情報発信やメルマガの認知拡大などでオウンドメディアが必要になります。
オウンドメディアは自社で制作することが可能ですが、立ち上げから運用までに以下の手順が必要となり、時間がかかります。
- オウンドメディアの目的を決める・・コンテンツの整合性を図るため
- 集客チャネルを考える・・どこからアクセスを集めるかを考える
- オウンドメディアの制作方法を決める・・すべて自社で実施するか外注するか
- オウンドメディアの設計を考える・・ユーザーが移動しやすい導線づくり
- オウンドメディアのデザインを考える・・ユーザーが離脱しないデザインづくり
- 記事を制作する・・ユーザーが求める情報を網羅する
オウンドメディアの立ち上げでは専門知識が必要不可欠なので、難しいようであれば外注も視野に入れておきましょう。
Webサイトの制作にかかる費用は?

Webサイトの制作費用は、サービスにもよりますが20万円からと高額なので、ここまでコストをかけられない企業も多いでしょう。
しかし、Webサイト制作サービスの中には、税込10,000円台で提供している企業もあります。
「ばりよか-BARIYOKA-」には、税込5,280円から利用できるプランがありますが、サービスの質が悪いわけではありません。
Webサイトの制作費用が高いからといって、外注化することをあきらめる必要はありません。
ナーチャリングを理解して見込み客を育てよう
ナーチャリングは、顧客の単価や営業の効率アップに繋がる重要な手法だと解説しました。
見込み客の状態が変化することを念頭に置いて、適切な情報発信をすることがナーチャリングのポイントです。情報発信をする際は、Webサイトを中心に、SNSやメルマガなどさまざまな媒体を活用するといいでしょう。
Webサイトを制作したいときは、「ばりよか-BARIYOKA-」にご相談ください。